カラーコスメOEM国内トップシェアのトキワによるコラム
化粧品の成分基礎知識|OEM製造に必要な成分の選び方

化粧品OEMの製品開発で、成分選びに悩んでいませんか?
「どの成分をどれくらい配合すればいいのか」「安定した品質を実現させたい」「法規制への適切な対応方法を知りたい」など、化粧品の成分に関する疑問を持つ方もいるでしょう。
本記事では、はじめて化粧品OEMを始める方はもちろん、すでに製造経験のある方にも参考になる情報をご用意しました。化粧品OEMに携わる方々の疑問を解消できるよう、化粧品の基本成分から、成分選択時のポイント、法規制まで、実務に役立つ情報をわかりやすく解説しています。ぜひ最後までご覧ください。
化粧品のOEM製造をサポートいたします!
トキワでは、国内外問わずこれまでたくさんのプレステージブランド様からの信頼をいただき、高品質な製品を提供してまいりました。
豊富な実績と確かな技術力を活かし、化粧品OEMが初めての方でも安心してご依頼いただけるようサポートいたします。
目次
メイクアップ化粧品の基礎知識|5つの基本成分

メイクアップ化粧品の基本成分は主に「水性成分」「油性成分」「界面活性剤」「着色剤」「粉体」の5つから構成されています。これらの成分をどのように組み合わせるかによって、製品の使用感や効果が大きく変わってきます。
本章では、各成分の特長を解説していきます。
1.水性成分
水性成分は、リキッドファンデーションやリキッドアイシャドウといった液状メイクアップ製品において重要な役割を果たします。製品の使用感や性能に直接影響を与えるため、適切な水性成分の選定が重要です。
水性成分の主な役割は以下の通りです。
- ・油性成分と界面活性剤とを組み合わせることで安定したエマルション(乳化)製品を形成
- ・製品の質感をコントロール
- ・粉体の分散性向上
- ・塗布時の伸びやすさや均一な仕上がりをサポート
代表的な水性成分には、精製水やグリセリン、プロピレングリコールなどの保湿剤も含まれます。また、温泉水やハーブ水、果実水などの美肌効果のある特殊な水性成分が使用されるケースもあります。
2.油性成分
油性成分とは、水に溶けにくく、油に溶けやすい性質を持つ成分を指します。メイクアップ製品においては、発色性や化粧持ち、使用感に大きく影響を与える重要な成分です。
油性成分の主な役割は以下の通りです。
- ・なめらかな使用感と鮮やかな発色を実現
- ・皮脂や汗に強い化粧膜を形成し化粧持ちを向上
- ・ツヤ感や立体感のある仕上がりを演出
油性成分の選択は、製品の使用感や化粧持ち、発色性に大きく影響します。揮発性シリコーンオイル、エステル油、ワックス類、植物油脂など、目的に応じて適切な油性成分を選定することが重要です。
3.界面活性剤
界面活性剤は、分子内に水になじみやすい「親水基」と油になじみやすい「親油基」を併せ持つ物質の総称で、製品の安定性や使用感を向上させる成分として使用されています。
界面活性剤の主な役割は以下の通りです。
- ・水性成分と油性成分の乳化
- ・洗浄作用(クレンジング・洗顔料の場合)
- ・のび広がりや密着性を向上させ、心地よい使用感を実現
- ・経時による分離や変質を防ぎ、製品の安定性を向上させる
界面活性剤の選択は、製品の質感や安定性に大きく影響します。たとえば、ファンデーションでは、顔料の分散性を高めながら適度な油水分離を防ぐ界面活性剤を選択することで、均一な仕上がりと化粧持ちの良さを両立できます。製品特性に応じ、適切な種類と配合量を選定することが重要です。
4.着色剤
着色剤は、化粧品に色を付けるための成分です。口紅、アイシャドウ、ファンデーションなど、さまざまな化粧品に使用されています。
着色剤の主な役割は以下の通りです。
- ・化粧品に色を与える
- ・製品のイメージを向上させる
- ・肌のトーンを補正する
- ・ツヤ感やキラキラ感を与える
代表的な成分には、金属の酸化物や硫化物などを原料とした無機顔料、有機合成色素(タール色素)や動植物や微生物から抽出された色素である天然色素、ツヤ感やキラキラ感を与えるパール材やラメ材などが挙げられます。
5.粉体
粉体は、固体微粒子で、ファンデーションやアイシャドウ、フェイスパウダーなど、粉末状の化粧品に多く使用されています。
粉体の主な役割は以下の通りです。
- ・肌表面を滑らかにし光を反射することで、透明感やカバー力を与える
- ・皮脂を吸着し、テカリを抑える
- ・化粧品の感触や仕上がりを調整する
代表的な成分には、タルクやマイカ、シリカなどが挙げられます。どの成分を使用するかによって、製品の感触や仕上がりが変わります。
配合バランスが重要な理由

各成分は単独で機能するのではなく、相互に作用し合うことで製品全体の仕上がりや効果を生み出します。メイクアップ製品の開発においては、基本成分の配合バランスによって発色や使用感、化粧持ちなども変わってくるため、理想とする製品を実現するための適切な配合バランスが求められます。
1.製品の安定性
メイクアップ製品では、顔料やパール材などの粉体成分と油性成分のバランスが製品の安定性を大きく左右します。適切な配合バランスにより、色むらや粉体の沈降を防ぎ、長期保存での品質維持が可能になります。
また、口紅やクリーム製品には、形を保つための「ワックス類」(例えば合成ワックスやキャンデリラロウ)と、なめらかさを出すための油性成分が含まれています。2つの成分比率を調整することで、暑い季節でも溶けにくく、寒い季節でも固くなりすぎず、快適に使えるように作られています。
これにより、季節や環境を問わず快適な使用感が得られるようになっています。
2.使用感
粉体成分と油性成分の比率調整により、さらさらとしたタッチからクリーミーな質感まで、目的に応じた使用感を実現できます。たとえば、アイシャドウでは粉体比率を高めることでパウダリーな仕上がりに。油分を増やすことでしっとりとした質感に仕上げられます。のび広がりや密着性、化粧崩れのしにくさなども、成分の配合バランスでコントロール可能です。
3.効果の最大化
メイクアップ化粧品では、顔料やパール材などの粉体が、発色やツヤ感を生み出す重要な成分です。粉体の分散性を最適化し、適切な油性成分を選択することで、発色の良さやツヤ感を引き出せます。とくに、パール材を使用する場合、基材となる油性成分との組み合わせが輝きの表現に大きく影響します。
フィルムタイプのマスカラやアイライナーは、フィルムを作る樹脂成分と、それを柔らかくする成分のバランスで仕上がりが決まります。このバランスを調整することで、フィルムがしっかり密着し、水や汗に強い商品を作ることができます。
成分を選ぶうえで重要なポイント
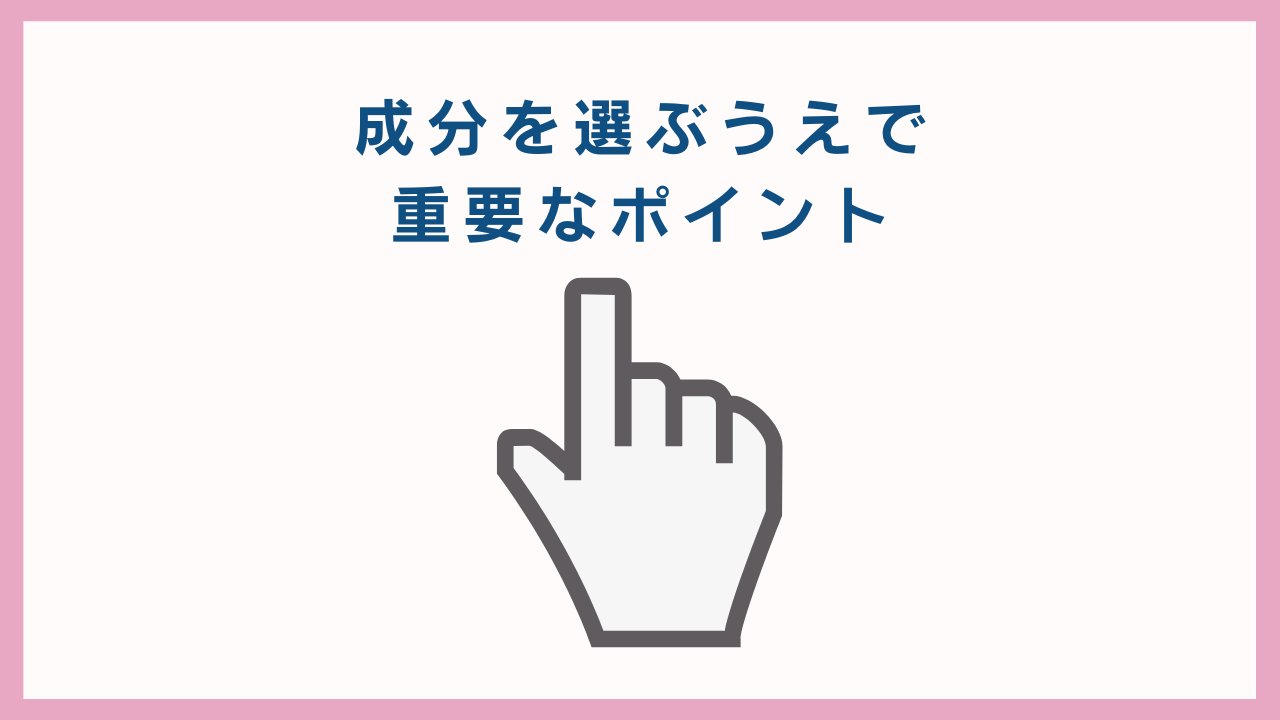
成分選定は、製品の発色性や使用感、化粧持ちなど、製品価値に直結する重要な要素です。効果的な差別化を図りながら安定した製品供給を実現するには、戦略的な成分選択が大切です。
本章では、メイクアップ化粧品の成分を選ぶ際の重要なポイントをご紹介します。すでに化粧品OEMを手がけている方にとっても、製品ラインの拡充や既存製品の改良を検討する際の判断基準となるでしょう。
1.コストと効果のバランス
製品の発色性や化粧持ちは、使用する成分に大きく左右されます。顔料やパール材は製品の仕上がりに影響を与える成分であるため、目的に応じた成分選定が重要です。
とくに、パール材の粒子径や光沢は製品の見た目を大きく左右します。高品質なパール材は製品の視覚的な魅力を高める効果が期待できますが、コストも比例して上昇。そのため、製品コンセプトや価格帯に応じ、最適なグレード選択が重要になります。
口紅やファンデーションでは、油性成分の選定が使用感と化粧持ちを左右します。製品の特性に応じ、これらの成分をバランスよく組み合わせることで、コストを抑えながら目的の使用感や仕上がりを実現できます。
2.原料の安定供給
メイクアップ化粧品では、色調の一貫性を保つために原料供給の安定性が非常に重要です。市場で人気を獲得し順調に販売数が伸びていても、原料調達が不安定では事業の持続的な成長は望めません。
そのため、気候条件の影響を受けやすいとされている天然由来成分を使用する場合は原料特性を深く理解しておく必要があります。とくに収穫量や価格の変動リスクがある成分の使用を考えている場合、OEMメーカーとも相談し、安定供給が可能な原料の選定や代替原料の確保を検討することも重要です。
新製品の開発時には、原料の市場動向と供給状況について十分な情報収集を行い、OEMメーカーとの連携を強化することで、将来的な調達リスクを軽減できるでしょう。
3.トレンドへの対応
化粧品市場は、ファッションやビューティートレンドの影響を強く受ける分野です。そのため成分を選ぶ際は、現在のトレンドだけでなく、今後の市場動向も考慮する必要があります。
たとえば、近年では環境への配慮から、天然由来のスクラブ材や、生分解性グリッター、天然由来のパール材など環境負荷の少ない成分への注目が高まっています。また、低刺激性の顔料やスキンケア成分を配合したメイクアップ製品が注目を集める一方、SNS映えを意識した鮮やかな発色や独特の光沢感を持つ新素材の需要も高まっています。これらの新素材は、従来にない効果や使用感を実現できる反面、安定性の確認や処方開発に時間がかかる場合があります。
トレンドに対応した成分を採用する際は、製品開発期間や市場投入のタイミングを考慮し、OEMメーカーと綿密な開発スケジュールの調整を行うことが重要です。流行に左右されない定番製品と、トレンド対応製品を組み合わせたバランスの良いラインナップを構築することで、持続的な競争力を保つことができるでしょう。
化粧品成分に関する法規制と表示ルール
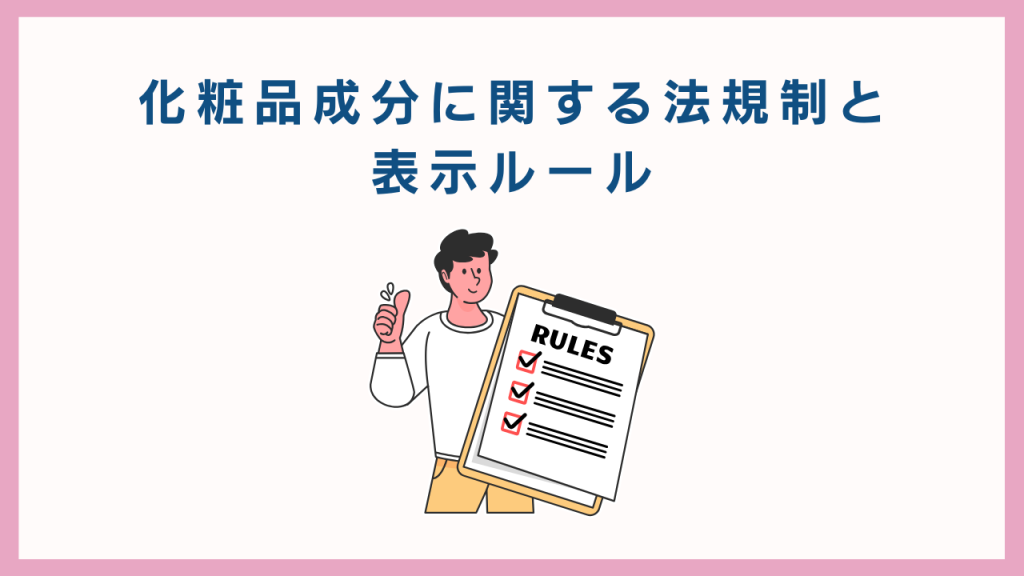
化粧品の製造販売には、厚生労働省が定めるさまざまな法規制が存在します。これらの規制は、消費者の安全を守り、適切な情報提供を確保するために設けられているものです。
化粧品OEMでビジネスを展開する際、これらの法規制と表示ルールを理解することは、製品開発から市場投入まで、すべてのプロセスに関わる重要な知識となります。
ポジティブリストとネガティブリスト
化粧品の成分規制において、ポジティブリストとネガティブリストという基準が存在します。これは、2001年4月1日の薬事法改正により、「化粧品基準」として厚生労働省によって正式に定められたものです。
ポジティブリストとは、化粧品への使用が認められている成分のリストです。防腐剤、紫外線吸収剤、タール色素などの成分については使用可能な成分が明確に定められています。
ネガティブリストとは、化粧品に配合してはいけない成分を示すリストです。このリストには、人体に対する危険性があるとされる成分や、特定の用途において不適切とされる成分が含まれています。たとえば、重金属や特定の有害化学物質などが含まれ、これらの成分は健康や安全に対するリスクが高いため、使用が許可されていません。
日本では、化粧品基準に基づき、すべての化粧品はこれらのリストに適合している必要があります。製造販売業者は、自社製品がポジティブリストに記載された成分のみを使用し、ネガティブリストに記載された成分を避ける責任があります。全成分表示が義務付けられているため、消費者はいつでも製品の成分確認が可能です。
これらのリストに基づく成分管理は、基本的にOEMメーカーが責任を持って対応しますが、基本的な知識でもあるため理解しておくとよいでしょう。
※参照:化粧品基準
全成分表示のルール
化粧品の全成分表示のルールは、消費者が製品に含まれる成分を理解し、安全に使用できるようにするためのものです。以下に、主なルールを詳しく説明します。
全成分の表示義務
日本では、化粧品に使用されているすべての原料の成分名を、製品の容器またはパッケージにわかりやすく表示することが義務付けられています。
配合量の多い順に記載
成分は配合量が多い順に記載されます。ただし、1%以下の成分については順不同で記載することが許可されています。
キャリーオーバー成分の非表示
キャリーオーバー成分とは、原料中に含まれるが製品中ではその効果を発揮しない微量の成分です。これらは表示する必要がありません。たとえば、防腐剤や酸化防止剤などが該当します。
香料の表示
香料は複数の成分から構成されているため、「香料」とまとめて表示することが認められています。
着色剤の表示
着色剤については、基剤成分の後に順不同で記載できます。
文字サイズの規定
文字サイズについては、基本的に7ポイント以上で表示することが求められています。ただし、表示面積が狭い場合や特別な事情がある場合には、4.5ポイント以上のサイズでも認められることがあります。
まとめ
化粧品のOEM製造において、成分や規制に関する正しい知識は必要な情報です。基本成分の特性を理解し、適切な配合バランスを実現することで、安定した品質の製品開発が可能となります。また、法規制への対応や原料の安定供給など、ビジネス面における考慮も重要です。
最新の規制動向や原料情報については、定期的な情報収集が求められます。不明な点がございましたら、お気軽にトキワまでご相談ください。

