カラーコスメOEM国内トップシェアのトキワによるコラム
化粧品の全成分表示ルールとは?初心者にもわかる基本とOEM担当者が押さえるべきポイント
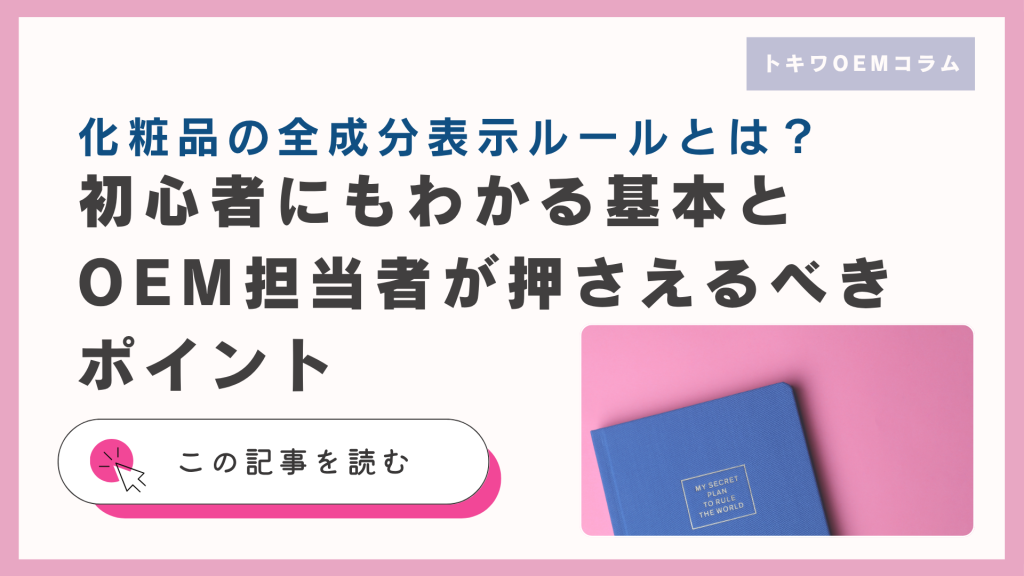
化粧品の裏面にある「全成分表示」は、法律で決められた正確なルールがあります。本記事では、全成分表示とは何か、その背景にある薬機法や消費者保護の目的や表示方法のルール、医薬部外品との違いまで網羅的に解説。
初心者でもスムーズに理解できるよう、配合順や特殊成分の扱いや表示名称の調べ方、OEM連携時の注意点など、重要なポイントに絞ってわかりやすく説明します。
目次
化粧品の全成分表示ルールとは?その背景と消費者保護の重要性
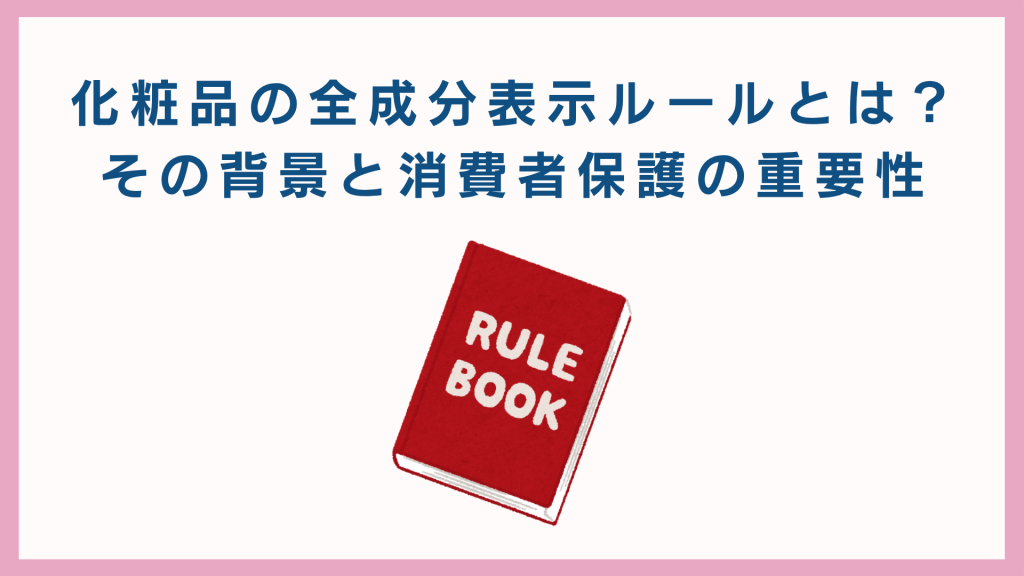
化粧品のパッケージ裏面などに記載されている「全成分表示」は、2001年から薬機法(旧・薬事法)によって義務化されました。これは、化粧品に含まれるすべての成分を配合量の多い順に、消費者から見えるところに記載しなくてはならないというルールです。
このルールが導入される前は、日本の化粧品は厚生労働省などの行政が製品ごとに「製造承認」を与える仕組みで、国が製品の安全性を保証していました。しかし、2001年の薬事法改正によりこの制度は廃止され、メーカーが自らの責任で製品の安全性を確保する「自己責任制」へと移行。これにより、消費者が自分で製品を選ぶために、より透明性の高い情報提供が求められるようになりました。
そのため、アレルギーを持つ人や肌が敏感な人が自分に合わない成分を避けたり、万が一肌トラブルが起きた際に原因を特定しやすくしたりするなど、消費者の安全を守ることを目的に「全成分表示」が導入されました。これは、単に化粧品に含まれる成分を並べるだけでなく、消費者の「知る権利」と「選ぶ権利」を守り、安心して化粧品を使えるようにするための重要な仕組みです。
これだけは押さえたい!化粧品の全成分表示、3つの大原則
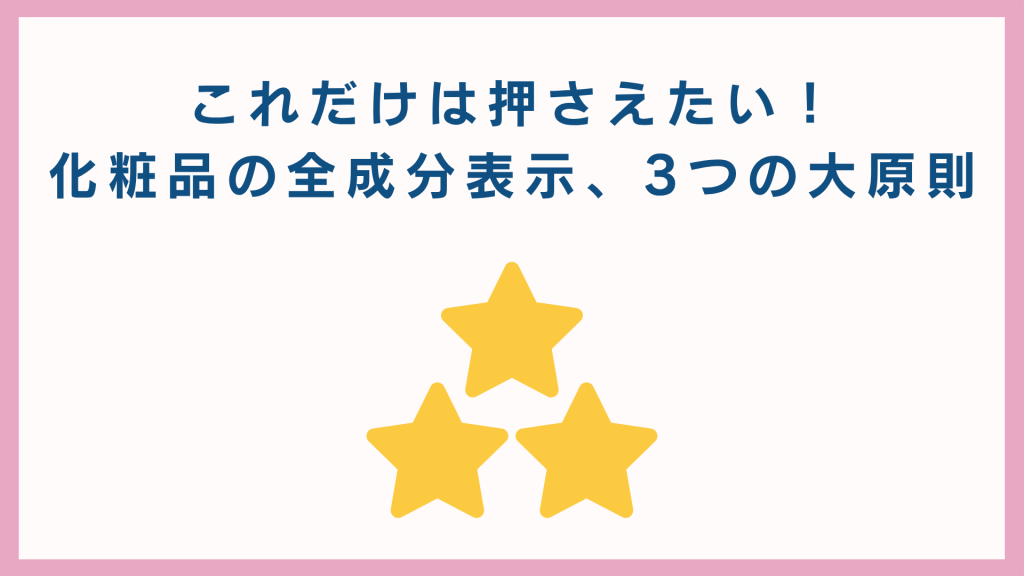
化粧品の全成分表示を理解する上で、基本となる3つの大原則があります。これらのルールを押さえておくだけで、成分表示の意図をより深く理解でき、OEMメーカーとの打ち合わせもスムーズに進められます。
原則①:配合量の多い順に記載する
全成分は、製品に含まれる量が多い順に記載するのが基本的なルールです。
例えば、化粧水であれば基剤である「水」が最初に記載されることがほとんどですが、メイクアップ化粧品の場合は、その製品の剤形(パウダー、リキッド、クリームなど)によって主成分は大きく異なります。そのため、オイルやシリコーンなど、その製品の骨格となる成分が最初に記載されます。
この原則によって、消費者は製品の中心となる主成分が何かをすぐに把握でき、どのような特徴を持つ製品なのかを大まかに理解できます。
原則②:「1%の壁」を理解する
配合量が1%以下の成分は、ルール上、順不同で記載できます。
そのため、アピールしたい美容成分などを(1%以下の範囲で)前方に記載することも可能です。
実務上、このルールを用いて、美容効果を訴求する成分や使用感を向上させるための添加剤などを先に記載し、防腐剤などをグループの最後にまとめる、といった対応をするケースが多くあります。
原則③:着色剤・香料・キャリーオーバー成分の扱いを知る
着色剤については、配合量にかかわらず、全成分表示欄の最後に他の成分とは区別しまとめて表示できるという特徴があります。
香料は通常、複数の原料を組み合わせて作られますが、すべての原料を細かく個別に記載する必要はありません。「香料」とまとめて総称で表示することが認められています。
「キャリーオーバー成分」とは、抽出や加工の過程でごく微量に混入した成分のことです。これらの成分は、最終的な製品の品質や機能に影響しない範囲であれば、成分表示を省略できます。ただし、消費者の安全性や情報提供に支障がない場合に限られるルールです。
表示名称に使用する名称や文字の大きさ
表示名称については、日本化粧品工業連合会が作成した「成分表示名称リスト」という公的なリストに掲載されている名称を使用します。一方、医薬部外品は、国から承認を受けたときに指定される「薬事承認名称」をそのまま記載するのが基本です。
ラベルやパッケージに記載する場合は、容器本体または外箱に、すべての成分を読みやすい文字サイズで記載する必要があります。通常は7ポイント以上、小さな容器の場合でも4.5ポイント以上の文字サイズで表示することが推奨されています。
化粧品と医薬部外品(薬用化粧品)の違い

化粧品と医薬部外品では、成分表示のルールに違いがあります。
医薬部外品の場合、法律上は全成分の表示義務がなく、特定成分(「表示指定成分」や香料など)だけを表示すれば良いとされています。しかし、近年は業界団体が自主的なルール(自主基準)を設け、医薬部外品でも全成分を表示するメーカーが増加。これは、消費者の安全意識や透明性へのニーズの高まりに応えるためであり、法的義務を超えて「よりわかりやすく、親切な表示」を目指す動きです。
将来的に「シワ改善」や「美白」などをうたった薬用化粧品(医薬部外品)の展開を検討している場合は、両者の違いを必ず理解しておく必要があります。
商品コンセプトによって、どちらで申請すべきかが変わります。
| 化粧品 | 医薬部外品(薬用化粧品) | |
|---|---|---|
| 表示義務 | 原則、全成分を表示 | 厚生労働省が指定した成分のみ(現在は全成分表示が強く推奨されている) |
| 成分の順序 | 配合量の多い順 | 規定なし(順不同でOK) |
| 特徴 | 特になし | 「有効成分」と「その他の成分」を明確に分けて記載する必要がある |
知らなかったでは済まされない「例外ルール」
例外として、複数の成分をあらかじめ混ぜ合わせて1つの原料として仕入れる「プレミックス原料(混合原料)」を使用する際、その構成成分を個別表記する必要があります。
化粧品の成分表示では、このような混合原料をそのまま「○○プレミックス」と書くのではなく、中に含まれている全成分を一つひとつ個別に表示しなければなりません。これは、消費者がその製品に何が含まれているのかを正確に知ることができるようにするためのルールです。
抽出物を使用している場合も注意が必要
植物エキスなど「抽出物」を使用している場合、その成分を抽出するために使われた「溶媒」(例:水、エタノールなど)が最終製品にも残る場合は、溶媒も成分として表示することが必要です。たとえば、ハーブエキス(抽出溶媒:エタノール)を配合し、製品にもエタノールが残っていれば、「ハーブエキス」「エタノール」の両方を成分欄に記載します。抽出後に溶媒が完全に除去されている場合は、溶媒の表示を省略できます。
さらに、表示名称(INCI名など)の誤りや、省略ルールの誤用(たとえば、キャリーオーバー成分でないのに表示を省略した場合など)が、実務上のトラブルにつながることがあるため注意が必要です。
全成分表示ルールに違反した場合のリスク
違反があった場合、薬機法や公正競争規約に基づく処分や販売差し止めのリスクがあります。成分表示のミスが原因で、消費者が健康被害などのトラブルに遭った場合には、「PL法(製造物責任法)」という法律が適用される可能性があります。PL法とは、製品の欠陥によって消費者が損害を受けたとき、メーカーや販売者が損害賠償責任を負うという法律です。
現代では、SNSなどを通じて情報が瞬時に拡散されるため、たった一度のミスがブランドイメージに致命的なダメージを与え、事業の存続自体を揺るがす可能性があります。こうした事態を避けるためにも、全成分表示は細心の注意を払って管理する必要があります。
OEMメーカーと連携する際に事業責任者が最終チェックすべきこと
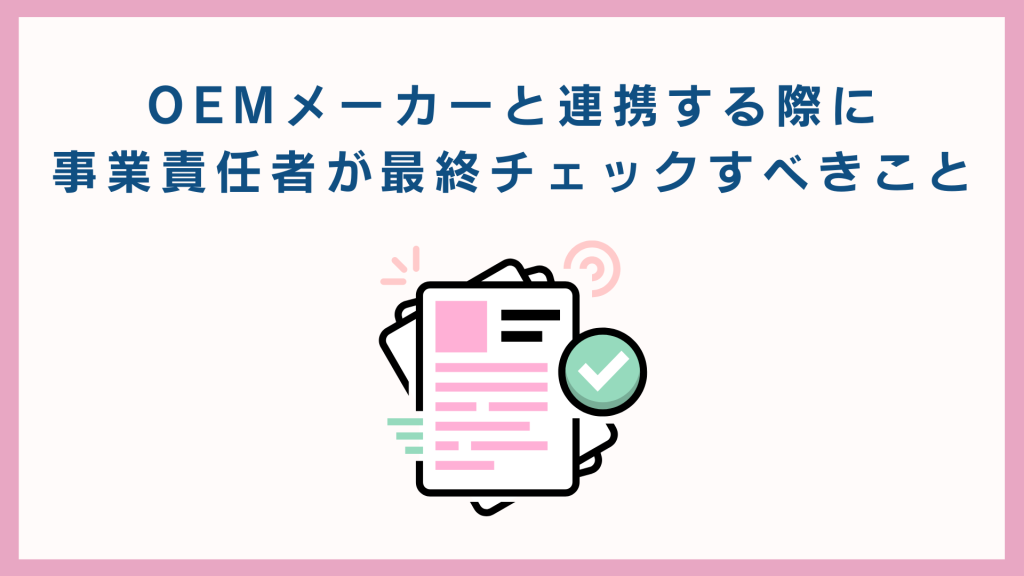
化粧品開発をOEMメーカーに委託する場合でも、表示内容に関する最終的な責任は販売元である自社が負います。専門的な部分をすべて任せきりにするのではなく、事業責任者として必ず最終確認を行うことが大切です。
特に以下の点は、主体的にチェックしましょう。
| ■表示名称の再確認 企画段階の成分名が、日本化粧品工業連合会(粧工連)の定める正式な「表示名称」と一致しているか、必ず確認してください。 ■例外ルールの適用判断 「この成分はキャリーオーバーとして扱って問題ないか?」「プレミックス原料の成分はすべて展開されているか?」など、例外ルールの適用が適切かどうかをOEMメーカーに具体的に質問し、その判断根拠を明確にしてもらいましょう。 ■表示順序の妥当性 配合量1%以下の成分の並び順について、「この順序が、消費者に最も誠実に製品特徴を伝える表示と言えるか?」という視点でOEMメーカーと協議し、マーケティング的な意図と消費者への配慮のバランスを取ることが大切です。 |
これらの確認を怠ると、意図せず法令違反を犯してしまい、ブランドの信頼を失うことにつながります。OEMメーカーとの打ち合わせでは、上記の質問リストを活用し、主体的に関与するよう心掛けましょう。
まとめ
化粧品の「全成分表示ルール」は、消費者の安心とブランドの信頼性を支える重要な制度です。本記事では、基本となる表示義務の背景から、配合順・例外ルール、医薬部外品との違い、実務で注意すべきポイントを整理しました。まずは「表示名称」「順序」「表示場所・文字サイズ」の3点を実務で意識し、OEMとの連携時には確認項目を明確にしておくことが重要です。
トキワでは、法律やルールへの理解だけでなく、サステナブルな容器設計と処方の両立など、独自の強みを活かしたOEM支援を行っています。これらの強みを活用し、適切に連携することで、安全で誠実にブランドの理念を伝える製品づくりが可能です。ぜひ、お気軽にご相談ください。

